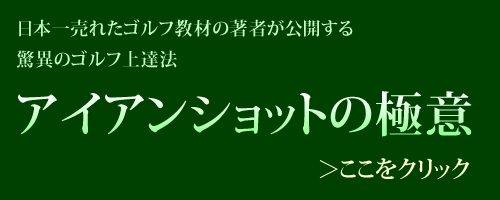ショートウッドとロングアイアン
ロングアイアンがどちらかと言えば苦手だと感じているゴルファーは意外に多いものです。
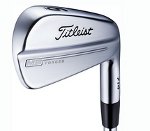 そんな方は、ロングアイアンの代わりにショートウッドを使用するという方法もあります。
そんな方は、ロングアイアンの代わりにショートウッドを使用するという方法もあります。
ショートウッドをロングアイアンと同じ要領で腰をレベルに回すことで、思いの他簡単に使いこなせるものです。
ロングアイアンの代わりにショートウッドを使用するというのは、例えばですが3番アイアンの代わりに、7番ウッドを加えておくといった具合です。
ショートウッドの方が、ボールが上がりやすい上に、飛距離も稼ぐことが出来ます。そのため、アベレージゴルファーにもうってつけで簡単にゴルフスイングをマスターすることが出来ます。
ショートウッドの基本的なスイング方法としてはアイアンショットと同様に、極端なダウンブローは避けることです。
あくまでも腰をレベルに回転させましょう。ショートウッドは高い弾道を描くため、直接グリーンにボールを落としたいシチュエーションでは活躍してくれるクラブです。
アドレスと同じロフト角でインパクトするイメージ
 ショートウッドで、すくい上げでボールを打ってしまうと、インパクトでクラブヘッドが手よりも目標方向に出るフォームになってしまいます。
ショートウッドで、すくい上げでボールを打ってしまうと、インパクトでクラブヘッドが手よりも目標方向に出るフォームになってしまいます。
これではクラブをアドレス時よりもロフト角が大きくなり、ボールが上がりすぎます。
さらに、ショットの方向性も悪くなりコントロール性が良くありません。アドレスと同じロフト角か、さもなければそれよりもフェース面を少し立てるような意識でボールを打つと、飛距離が伸びて方向性もずっと安定します。
ショートウッドに特有な性質である、幅広いソールがグリーンの上を滑り、スムーズに振り抜くことができるのです。
フェアウェイウッドの振り方
スポンサード リンク
基本的にはヘッドを地面に滑らせるように意識したゴルフスイングをすれば良いのです。
アイアンと比較して、非力な人でも飛距離が出るのがフェアウェイウッドの魅力でしょう。シニアやレディースならばなおのこと武器にしたいクラブです。
フェアウェイウッドの特徴は、ソール(ヘッドの底)が広いことはすでに述べました。このソールを利用して、ヘッドを芝の上で滑らせるようにして打つのが理想的です。
イメージとしては、ほうきで地面を掃くような感じで良いのです。ゴルフスイング全体としては、ゆっくりと大きな円を描くように振ることです。
中にはどうしてもフェアウェイウッドが上手く打てないという人もいるかもしれません。
その場合は、クラブを短めに握って、コンパクトなスイングで振ってみましょう。最近のフェアウェイウッドは、当たればそれなりに飛ぶように造られています。
ボールを意識的に上げようとしてはうまくいきません。普通に打つだけでボールは自然と上がります。
最もいけないのはボールを上げようとする動きです。ボールが上がりやすく元々できているので安心して使えます。
ロフト角もしっかりあるため、芯より下側に当たってもボールはある程度上がってくれます。
ロングアイアンの特徴
ロングアイアンの場合、失敗の連続から生まれた苦手意識を捨てることが必要です。ゴルフクラブの中でも最もスイングを壊しやすいのが、ロングアイアンだと指摘する声が多いです。
 クラブヘッドはどちらかと言えば小さく、そのうえシャフトが長くてロフトもないという厳しい条件。そのために自分の腕力に頼って飛ばそうとすることで、バランスを乱すというわけなのです。
クラブヘッドはどちらかと言えば小さく、そのうえシャフトが長くてロフトもないという厳しい条件。そのために自分の腕力に頼って飛ばそうとすることで、バランスを乱すというわけなのです。
このため、ロングアイアンで高い球を打つのはどちらかと言えば難しい部類になるでしょう、率直にいえば練習不足に起因する失敗がほとんどともいえます。
むずかしいクラブほど短く握って、ティアップして練習するようにすると効果的だという話もあります。
マットの上にボールを置いて、フルパワーで長く持って打とうとするから失敗するというのがその理由です。
一度でも失敗すると練習することの楽しさは半減するため練習すること自体がいやになります。そのため、いつまでたっても苦手意識が抜けきらない。だから、また失敗するという負のスパイラルです。
ロングアイアンだからといって、他のクラブと比べて特別な打ち方は必要ではないという人もいます。
スポンサード リンク
ボールをセットする位置はドライバーよりも1~2個くらい内側にして、打ち込んでいくという感覚ではなく横に払うイメージで振るというフェアウェイウッドに近い感覚が良いようです。
ならば、いっそのことショートウッドにしようかということになるわけです。
インパクトで当てようとして、調整しないことはどちらのクラブでも大切です。ボールに当てにいくと上からをプレスする形のインパクトが生まれてしまいます。
最初のうちはまっすぐに飛んだとしても、途中から勢いが台風のように急速に弱まって、スライスしていく球筋になることが多いです。
 ロングアイアンの打てない人は、ショートウッドにしないのであればまずはティアップして打ってみることをおすすめします。
ロングアイアンの打てない人は、ショートウッドにしないのであればまずはティアップして打ってみることをおすすめします。
多分打点もばらつくでしょうが、練習を繰り返していく根性があれば、どこに当たるとどんな打球になるかが感覚的につかめてくるかもしれません。
さらに、この場合トップ・オブ・スイングを大きくしないでスリークォーターで止めるようにしてみます。
フルスイングの練習を避ければ球筋は低くなるでしょうが、スライスやフックさえ出なければ、うまく打てている証しとも言えるでしょう。
ロングアイアンのようなむずかしいクラブほど、やさしくして打つことが自信にもつながってきますから、慣れてくれば、ふつうに打てるようになってくることも無きにしも非ずです。
ロングアイアンのポイント
テークバックというものは上半身と下半身の捻転差を生み出す非常に大切なプロセスと言えるでしょう。
この段階で右サイドヘ体がスエーするようなら、ボールを飛ばすエネルギーの源となる捻転差が生まれないことにあんります。何よりも右足全体で受け止める気持ちが必要です。
首の付け根をスイングの軸ととらえて、その軸を中心にしてターンしていくことになりますが、トップ・オブ・スイングのポジションでターゲット方向に上半身が流れてしまっては元も子もありません。
切り返しの際には、テークバックで右足に重心を移動させ、切り返しで左足に重心が移動していくことになります。
腰のターンが最初にあってでクラブを振り下ろしていくことになるので、クラブ自体はまだトップ・オブ・スイングに近い位置に止めましょう。
上半身と下半身の捻転差を生かしたアイアンショットができれば、インパクトで腰のラインは開く状態になるのが自然なことです。
両肩を結んだ肩のラインは、腰のラインと常にズレた動きをしているのが正しいフォームです。
スポンサード リンク
左手の甲の向きが、フェースローテーションをしているかしていないかの判断基準と考えられますから、フェースローテーションをしない方が方向性が安定することを想い出してください。
スイングを途中で止めてはいけません。まだまだ先までスイングを続けることによって、大きなスイングアークが実現できます。
そのため、自分の中の意識としては、ずっと先まで手を動かすようにと心がけるべきでしょう。
フィニッシュでは左足にしっかりと体重が乗っている状態を作りましょう。
フィニッシュでは自然に左足重心になるのですが、無理に左足に乗せるというのではなく、自然にスッと立てる状態が一番良いバランスになっていると言えるでしょう。
意外とやさしいフェアウェイウッドを使った転がし戦法
フェアウェイを短く握って掃く要領で使えば芝の上をソールが滑るというアプローチの手段にも使えます。意外と盲点なのがフェアウェイウッドを使った転がし作戦です。
 あまりアマチュアでは見慣れない方法なのは確かですが、実際にはタイガーウッズをはじめとするプロゴルファーもよく使っている方法で、ミスをする確率が低く楽に転がせるアプローチができるメリットがあります。
あまりアマチュアでは見慣れない方法なのは確かですが、実際にはタイガーウッズをはじめとするプロゴルファーもよく使っている方法で、ミスをする確率が低く楽に転がせるアプローチができるメリットがあります。
あえてここでウッドを採用する理由としては、アイアンクラブに比較してソール幅が広いという点にあります。
ソール幅が広いことのメリットとしては、リーディングエッジが突き剌さる可能性が減って、少しくらい手前から入ったとしても芝の上を滑っていってくれるという点です。
これほどのメリットがあるウッドでのアプローチを選ばずにアイアンクラブを使用する人が多い理由としては、シャフトが長いというところが原因のひとつです。
一般的には43インチの長さがフェアウェイウッドにはあるわけです。これを、めいっぱいの長さに持ってしまうと扱いにくいのは確かですから、大胆な方法を採用しなければなりません。
その方法とはグリップ部分を握るのではなく、シャフトを握るということです。大胆に短く持ちます。
 クラブを持つときには、必ずグリップ部分を握れとはルールブックには書かれていない点を利用するわけです。
クラブを持つときには、必ずグリップ部分を握れとはルールブックには書かれていない点を利用するわけです。
アドレスする際には、ハンドファーストに構えてシャフトが体に当たらないようにします。
グリップ部分は左のわきの方に逃がしてやる要領がここでの大きなポイントにあげられます。
ゴルフスイング自体は、ランニングアプローチやパターの要領を応用することで誰にでも対応可能でしょう。
できるだけクラブヘッドを地面から上げないようにする工夫が必要ですし、低く低く芝の上をスイープさせる要領で振っていけば良いのです。
スポンサード リンク
このため構え方に関しても、パターのことをイメージして両腕で五角形をつくり、その形をキープしたままストロークするようにすればうまくいくでしょう。
ウェッジやアイアンと比べてウッドはヘッドが軽いので抵抗に弱いという面があることは否定できません。
それを補う目的で、右手のグリップはしっかり握りこと、右手首の角度をずっと維持したまま振り抜くことを考えましょう。