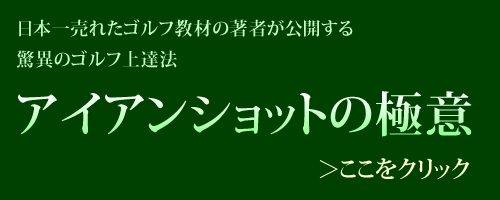アイアンのハンドファーストの構え方
ハンドファーストに打つということの意味は、クラブヘッドよりも手元が先行した形でインパクトするということを指示します。
そして、インパクト時にハンドファーストの状態がキープできていれば、基本的にはインパクト時の手の位置が、ヘッド軌道の最下点になって、ボールの先のターフを取ることができるということになります。
しかしながら、多くのアベレージゴルファーに見られるのは、ダウンスイングの早い段階で右手首をリリースしてしまっているようです。
そうなれば、手元よりもヘッドが先行した形でインパクトを迎える形になり、軌道の最下点はボールの手前側になってしまいます。
 ハンドファーストに打つためには、どうすればいいのかという点に関しては、切り返しでできた右手首の角度を、インパクトまで絶対に維持しようとする意識を持たなくてはいけません。
ハンドファーストに打つためには、どうすればいいのかという点に関しては、切り返しでできた右手首の角度を、インパクトまで絶対に維持しようとする意識を持たなくてはいけません。
また、右手首をリリースしてしまうタイプのゴルファーは、ヘッドを先行させようとして手元が減速しながらインパクトする傾向も見られます。
そのため、ヘッドを先行させようとする動きを抑え気味にして、手元を減速させずにインパクトする意識を持つことで、手首の角度を維持するためのコツと言えるでしょう。
アイアンのハンドファーストの構え方が正しくできれば、ハンドファーストインパクトでボールをクリーンにヒットすることができるようになるでしょう。
大部分のアマチュアゴルファーが理解できていないこととして、アイアンでロフトどおりにボールを打つという意味は、インパクトでロフトが少し立った状態のことであるという点が挙げられます。
構えたときと同じロフトでインパクトを迎えていると、それは少しクラブフェースが開いていることになるのです。
アマチュアのプレーの大半の場合、ボールをしゃくり上げようとするゴルフスイングをしている人がほとんどです。
結果的には、本来の状態よりも余計にフェースを開いたままインパクトを迎えることになるで、ロフトどおりの飛距離が出ないということになります。
スポンサード リンク
それからボールの上からヘッドを打ち込む形のスイングをして、無理に深いターフをとろうとする人も目立ちます。
しかし、これでは本来クラブが持つロフトよりももっと立った状態でボールをとらえることになります。
そのため、ボールが上がりません。ちょっと想像していただければなるほどと理解できるような話だと思います。
アイアンクラブの設計上のロフトどおりの飛距離、高さを出すためには、両手がボールよりも先にいくハンドファーストの形が必要です。
つまり、ボールをクリーンに打つイメージを持つ必要があるので、インパクトで左手のグローブのマークがターゲット方向を指していれば、ハンドファーストインパクトと考えればよいでしょう。
この場合に注意しなければいけない点としては、リストが甲側に折れないようにすることでしょう。
ハンドファーストの構えの作り方の前に
ハンドファーストの構えの作り方の前に、次のドリルが有効です。
 まずは、ハンドファーストの形をつくってから、そこからボールを飛ばしてみるようにしてみましょう。
まずは、ハンドファーストの形をつくってから、そこからボールを飛ばしてみるようにしてみましょう。
ハンドファーストインパクトを実感できない場合は、まず、インパクトの姿勢を先に作ってから、バックスイング方向にクラブを上げずに、フォロースルー方向に振り出してみましょう。
そして、実際にボールを飛ばしてみましょう。
クラブフェースにボールを乗せるようなイメージでスイングすることになりますが、ハンドファーストの姿勢が正しく出来ていないと、ボールを飛ばすことはできないでしょう。
クラブヘッドの直線的な動き
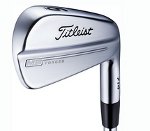 フェアウエーにあるボールをアイアンで打てば普通であればターフがとれますが、大切なのはターフの形と場所です。
フェアウエーにあるボールをアイアンで打てば普通であればターフがとれますが、大切なのはターフの形と場所です。
ボールが元あった場所から目標に向かって薄くて長いターフがとれていれば、ボールをうまく打てた証拠にもなりす。
ところが、ボールのあった場所の手前からターフがとれていたり、深くて短いターフの跡が残っているようでは、ボールを正確にとらえていない可能性が高いのです。
ボールよりも先の地点でターフを薄く長くとれるようになるには、長いインパクトゾーンをつくることが必要条件となります。
ハンドファーストに構えた時から始まってクラブが下りてきた時点でヘッドが左足の前を通過するまでの間、直線的にクラブを動かしていることになるのです。
スポンサード リンク
結果的にはフェースがターゲットに対してスクエアになる状態を長くキ-プできていることになるので、理想のターフだということが言えるわけです。
インパクトしてから、左足にウエートを乗せて、そのままターゲットに向かってクラブフェースでボールを押していくような感覚です。
これがマスターできれば、ボールの回転数と打ち出し角度がいつでも安定した状態になって常に同じ弾道でボールを打てるようになるでしょう。
トップ・オブ・スイングからフィニッシュさまで同調
アイアンショットの場合には、体と腕を同調させることは「シンクロ」するという表現でこれまで述べてきました。
 フルスイングであれば、その同調感を意識できる箇所が右ヒザの高さから左ヒザの高さまでになっても問題ありません。その部分さえしっかりできていれば、体と腕をシンクロしたゴルフスイングといえます。
フルスイングであれば、その同調感を意識できる箇所が右ヒザの高さから左ヒザの高さまでになっても問題ありません。その部分さえしっかりできていれば、体と腕をシンクロしたゴルフスイングといえます。
しかし、ラインを出すことが目的のスリークォータースイングの場合には話が少し違います。アドレスからフィニッシュまでずっと体と腕がシンクロしていなければいけません。
それがうまくできていないと、ボールを狙ったところに打ち出せないということになるでしょう。
体の前方にいつでも両手があるようなアイアンショットを心がけましょう。
インパクトでフェースを返したりする動きを行う必要は全然ありません。腰をしっかりと回転させてクラブを戻してくるだけで良いのです。
こうすることでインパクトでクラブフェースがスクエアな状態に戻りやすいというメリットがあり、ボールからピンまで線を引いたようなショット(つまりライン出し)を打てるということです。
プロゴルファーなら技術的なレベルが高いので3番アイアンでもこの打ち方をできるのかもしれませんが、アマチュアゴルファーでも、練習を重ねることで8~9番アイアンくらいの長さなら必ずできるようになるでしょう。
両ワキを締めスイングする
ライン出しのショットの場合は、より体と腕をシンクロさせる必要が高いのですが、トップ・オブ・スイングやフィニッシュで両脇があかないように注意しましょう。
ハンドファーストに構えた時点からしっかりと両ワキを締めたゴルフスイングを意識すると体の動きに腕がついてくるようになるでしょう。
クラブを手にしないで、腕を普通に伸ばした状態でシャドースイングをしてみて、両ワキが開かないように気をつけながら、体を回してみてチェックしてみましょう。
インパクトからはヘッドだけを先行させない
スポンサード リンク
ライン出しのショットの場合、インパクトからはヘッドだけを先行させないように注意します。クラブのフェース面が常に体と一緒に動くのが正しいライン出しのアイアンショットなのです。
ヘッドだけが先行してしまうとクラブのフェース面の向きが変わりやすくて、ボールを狙ったところに打ち出せないことが増えてしまうでしょう。
その上に、インパクトゾーンを長くとることが難しくなるため、ボールに加わるスピン量も一定に保つことが困難になり、弾道にもバラツキが生まれやすくなるでしょう。
アイアンショットの最中はハンドファーストに構えた時点からはじまってグリップエンドを常に自分のヘソに向けたままクラブを振りますが、インパクトした後は特にこの点に意識を集めましょう。
これがマスターできれば、インパクト以降でも体の動きに連動してクラブヘッドが動く状態になるため、クラブヘッドだけが先行することは起きないでしょう。
 その上、インパクト後に両手が体から離れていかないように、できるだけ体の近くを通すように心がければ言うことなしです。
その上、インパクト後に両手が体から離れていかないように、できるだけ体の近くを通すように心がければ言うことなしです。
ただし、フルスイングともなるとちょっと違ってきます。
この場合はヘッドスピードが上がるので、多少ヘッドが先行しても構わないと考えてください。
ダウンスイングのポイント
ダウンスイングで左ワキが開いたり、フォロースルーで左ヒジが引けたりすることは避けるようにしましょう。
ダウンスイングで左ワキが空いてしまうと、インパクトでフェースの向きが変わるので方向性が不安定になるということは先ほどの説明の通りです。
また、フォロースルーで左ヒジが引けてしまうと、これもヘッドだけが先行して、やはりフェース面が変わる結果となるので、ラインを出すのが難しくなります。
アイアンショットではいつでもグリップエンドをヘソに向けるようにハンドファーストに構えた時から気を配りましょう。