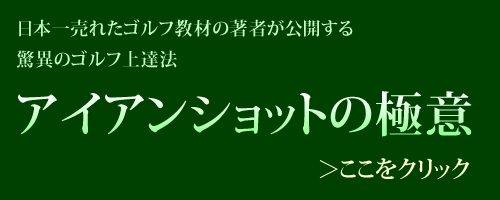アイアンショットの正しい道
正しい基本のアイアンショットをするにはクラブヘッドが落ちそうになるのを我慢しながら振り抜くこととも言えるでしょう。
一旦、ゴルフクラブが動き始めれば、そこに慣性というものが埋めれてきます。これがドライバーショットならば慣性を生かして振ることでスピードアップを図ります。
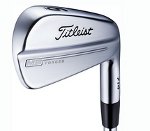 けれども、飛ばすことが真の目的ではないアイアンショットの場合においては、ある程度慣性を殺すような感じでスイングするというテクニックが要求されます。
けれども、飛ばすことが真の目的ではないアイアンショットの場合においては、ある程度慣性を殺すような感じでスイングするというテクニックが要求されます。
慣性を殺しながらスイングするということが意味するのは、アイアンクラブを寝かさずに振ることとも言えます。
これがコントロールショットの基本的な考え方といっても構わないくらいです。もちろん慣性を生かして振るような状況もあることはありますが、基本は慣性を殺してクラブコントロールするという状況が圧倒的なのです。
慣性を殺すときに大切なことは、手とクラブの角度を維持しながらスイングするということです。ダウンスイングが始まることでアイアンのクラブヘッドは下落しようとします。
けれども、手首に力を入れることでそれを阻止するのです。このようなスイングうをすると、正面から見た軌道は、ドライバーのU字型に対してアイアンはV字型と言えるでしょう。
この軌道の違いがあるからこそ鋭角な入射角を確保することが可能になってライの状況が悪くてもそれなりに対応することが可能になります。
とは言っても、いくら手の角度をキープしてクラブを立てようと意識しても、実際のところ慣性に勝てずに完全に慣性を殺すショートアプローチの軌道どおりにはクラブは下りてくれません。
 立てている感覚を持っていながらもダウンスイングではオンプレーン上を下りてきて、フォロースルーに至っては立ってくることでしょう。
立てている感覚を持っていながらもダウンスイングではオンプレーン上を下りてきて、フォロースルーに至っては立ってくることでしょう。
クラブをまったく寝かさないで振ることが可能なのはサンドウェッジで、60ヤードぐらいのショットまでが限度でしょう。
つまり、8番アイアンのコントロールショットをする場合には実際には慣性に負けてしまうはずです。勝てないということはわかっていながらも同じ感覚でスイングすることが大切なことなのです。
骨盤の動きによってスイングタイプは分かれる
スポンサード リンク
ゴルフスイングというものは骨盤の使い方の違いで、大きく2つのタイプに分類しようとすればできないこと。
第一のタイプは、骨盤を左右にスライドさせる動きをすることで、ダイナミックに身体を動かすゴルフスイングです。
これに該当するのはタイガー・ウッズです。
バックスイングでは体重を右股関節にのせ、フォロースイングでは左股関節にのせてターンする2軸回転系のスイングで、一般的には「2軸スイング」と呼ばれることが多いタイプです。
このタイプは重心移動量が大きくて、腕のロ-テーションを抑制しながらクラブを直線的なイメージで振り抜いていくのが特徴的です。
第二のタイプは、骨盤をその場で回転させるスイングで1軸回転系の昔から欧米で一般的なスイングスタイルです。これに該当するのは、ボビー・ジョーンズ、バイロン・ネルソンといった選手です。
 このタイプは重心移動量が小さくて、腕をやわらかくローテーションさせながら円運動のイメージでクラブを振る方法で、一般的には「1軸スイング」と呼ばれることが多いタイプです。
このタイプは重心移動量が小さくて、腕をやわらかくローテーションさせながら円運動のイメージでクラブを振る方法で、一般的には「1軸スイング」と呼ばれることが多いタイプです。
ここでは、どちらが優れているとか劣っているという話ではありません。どちらのスイングスタイルも問題ありません。こうした違いは個性ととらえても構わないのです。
 原則としてアイアンでのスイングでは左右対称になっているという点が守られている限り、どちらのタイプに属していてもいいのです。
原則としてアイアンでのスイングでは左右対称になっているという点が守られている限り、どちらのタイプに属していてもいいのです。
ただ、1軸スイングはより強い肉体的なパワーが必要だということははっきりと言えると思います。だから、パワーヒッターに多いタイプなのです。
気をつけなければいけなことは、1軸スイングと2軸スイングでは、トレーニングや練習の方法が必ずしも同じではない場合があるという点です。
直線的なイメージの1軸型のスイングをするゴルファーが、円運動のイメージをマスターするトレーニングをすることがないように気をつけなければいけません。
逆もまたしかりで、そのドリルがどちらのタイプに適したものなのかを、よく吟味してから実行しなければいけません。
ただ、実際問題としては、アイアンショットの場合はどちらか一方のスイングだけをマスターするのでは不十分です。
2軸型の選手でも、1軸回転で打たなければならない状況も実戦では出てくるわけです。たとえばひどくつま先下がりの傾斜など、足場の悪い状況では重心移動がほとんどできません。
そういう場合には体を固定しますから、1軸タイプのコンパクトな技術でのゴルフスイングも必要とされるのです。
2軸スイングは腕回りを硬くして動かす
スポンサード リンク
2軸型のスイングは慣性を殺しながら振る動作となって弾道の高さを抑えて、ターゲットを狙い打ちするようなイメージの強いスイングと言えるでしょう。
具体的には、腕を硬く使うような感覚で腕とフェースのローテーションを抑えながらスイングすることになります。
体の動きとしては、頭の動きは下半身よりも少なく、骨盤が左右にスライドするのが望ましいピラミッド型の動きです。
これは腕を硬く使うがために起きる必然性の高いボディモーションと考えるべきでしょう。
尾崎将司プロや中嶋常幸プロの技術はこのような硬さのあるテクニックで、だからこそローボールを打つのが得意だともいえるでしょう。
 腕周りは硬くした状態で体を大きく使うことで弾道は低くなって、ボールをターゲットまで「運ぶ」という感覚が強くなるわけです。
腕周りは硬くした状態で体を大きく使うことで弾道は低くなって、ボールをターゲットまで「運ぶ」という感覚が強くなるわけです。
その一方で、腕をやわらかく動かす1軸型のスイングでは「ボールをさばく」とか「シャープにスイングする」という感覚で表現できるものです。
このどちらの感覚でプレーするのがベストなのかは、自分の持つ身体的能力と感性に合わせて選択すればよい話であり、スイングの左右対称性さえ厳守出来ていればどちらでも問題ありません。
1軸タイプは下を向きながらスイングする
腕をやわらかくして使う1軸タイプのゴルフスイングは、慣性を生かす意味合いの強いショットとも言えるものです。
 しかし、慣性を生かして振ることのデメリットとして、球が上がりやすくなるという欠点が表面化してきますから、低い球筋を狙う場合には、体の使い方でそれをカバーする必要が出てきます。
しかし、慣性を生かして振ることのデメリットとして、球が上がりやすくなるという欠点が表面化してきますから、低い球筋を狙う場合には、体の使い方でそれをカバーする必要が出てきます。
では、具体的にどうすればいいかという方法論に移りますが、体幹を下に向けながら使うということになります。
これによってクラブヘッドが低く長く入ってくる感じになって、フォロースルーでも低く抜けていくために低弾道が生まれるわけです。
腕を硬めに使用する2軸型のスイングでは、タイガー・ウッズのように胸を張る姿勢になりますから、見た目はまったく逆のテクニックに見えるでしょう。
仮定の話ですが、その意味では胸を閉じてしまう癖がある場合は、思い切って1軸型のスイングにイメージチェンジしてしまうという方法も効果的な場合があります。
ワッグルの効果
スポンサード リンク
ゴルフスイングをスタートさせる前にワッグルすることでクラブを動かせば手の平でフェース面を感じやすくなります。
ゴルフクラブを左右に小さく動かすことをワッグルと呼んでいます。
ワッグルと視覚の両面でフェース面を感じるようになるでしょう。
フェース面の状態をしっかりと感知するために、ゴルフの上級者たちが無意識のうちに行なっているのがワッグルです。
クラブを静止させているとわからない重心というものが、かすかに動かすことでつかめるようになるのでフェース面の意識がより鮮明になります。
重心をしっかりと感じているからこそ、フェースかかぶってしまったとか、開いてしまったといった違和感を即座にわかるのです。
それはゴルフクラブの形状の特性に由来するものであって、シャフトの軸線と重心が一致しないことによるものです。
クラブの先に球のついているような練習用のクラブでは、シャフト軸線と重心が完全に同じになるので、ワッグルしても重心を感じ取ることはないでしょう。
言い換えれば、手の中でフェース面を感知するときのセンサーになるのが重心であり、視力でフェース面を感知するときの支えになるのがリーディングエッジなのです。
この2つを基準にして自分なりのスクエアを見つけるということがはじめて可能になるのです。