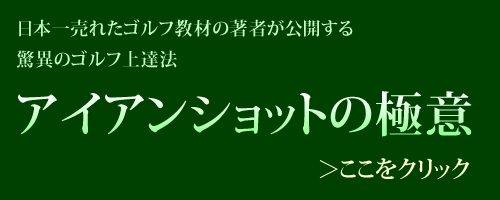ダフリ、トップを防ぐには
まずテークバックではグリップが右の腰付近に達するまで、リストは使わずにノーコックでクラブを上げていきます。
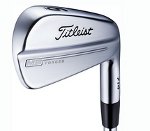 その際は、左肩、左腕の左サイドを大きく使いながら、クラブをできるだけ遠くに離して上げていく意識を持つことが大切です。
その際は、左肩、左腕の左サイドを大きく使いながら、クラブをできるだけ遠くに離して上げていく意識を持つことが大切です。
グリップが右腰を過ぎた付近からリストを使って、右耳の高さでストップさせます。これ以上バックスイングを大きく上げてしまうのはマイナスです。コンパクトなトップ・オブ・スイングを作ることを意識しましょう。
トップをコンパクトにするのは、オーバースイングになることがダフリ、トップのミスショットの一番の理由になるからです。
ダフリとトップは全く違うミスのように感じるかもしれませんが、根本的な原因はまったく同じものと考えてよいでしょう。
このミスショットの原因はオーバースイングになることの他に、もうひとつ体が上下動するゴルフスイングも要因として考えられます。
一度沈んだ体は、次には伸び上がろうとする動きになるのは自然なことです。
沈んだタイミングでボールをヒットしたら、ダフリになりますし、伸び上がったタイミングで打てば、トップが出てしまうわけです。この上下動のゴルフスイングになる原因は、手先でクラブを持ち上げているからです。
腰を軸に対して平行に回していくレベルスイングのようなバックスイングを心がけるとダフリ、トップが無くなる可能性があります。
レベルスイングと先ほどのコンパクトなトップの2点を心がければミスショットが改善できる可能性が大きくなるでしょう。
 アイアンショットでダフリ、トップのミスショットが出てしまうとスコアメイクに大変苦しむことになります。
アイアンショットでダフリ、トップのミスショットが出てしまうとスコアメイクに大変苦しむことになります。
練習場でアイアンクラブを振る時間の割合を今までよりももっと増やしてみればいかがでしょうか。ドライバーショットばかり続けていても上達は早まりません。
スポンサード リンク
ドライバー
 ダウンスイングで右肩が落ちる現象もひんぱんに見受けられます。ダフリやトップが出るのは主にダウンスイングで右肩が落ちるためです。
ダウンスイングで右肩が落ちる現象もひんぱんに見受けられます。ダフリやトップが出るのは主にダウンスイングで右肩が落ちるためです。
これは本能的にボールを上げてやろうというゴルファーに多く見られます。
例えばドライバーをとってみると、これはハンデ10台のゴルファーでも「易しい」と感じている人は少ないでしょう。特にボールがあがらないと嘆くゴルファーが多く見られます。
しかし、ティ・アップして普通に「払う」ように打てばロフトも11度以上はあるのだしティにのっていることもあって自然にボールはあがっていくはずです。
それを、どうあっても身体で上げようという気持ちが強く働らいてボールをすくい上げる打ち方になってしまうのです。この時に身体の自然な動きとして右肩が落ちるのです。
右肩が落ちることは、左肩が上がることにつながります。ボールを上げようと願うゴルファーはインパクトからフォロースルーにかけて完全に左サイドが伸び上がっているものです。
こういう状態を迎えるということはダウンスイングでからだの回転が行なわれていないためで、ヘッドのスピードも鈍るしダフルのは当たり前になるでしょう。
ダフルのがいやでさらに身体を伸ばしてすくい打ちの度合いを強めれば今度はトップになりやすいでしょう。
いずれにしろクラブヘッドは下から上へ動くのですから、ダフらなければクラブが下から上へあがりしなにボールの上を打って、トップになるわけです。
 こういう場合は、打った後は体重も左足にのらないで逆に右足にかかってくるでしょう。フィニッシュなど、とろうとしてもとれるものではありません。
こういう場合は、打った後は体重も左足にのらないで逆に右足にかかってくるでしょう。フィニッシュなど、とろうとしてもとれるものではありません。
これを直すには右肩を意識するよりも左肩に注意した方が良いでしょう。
左肩をむしろ沈み込ませるようにするのです。左サイドが伸びあがるのを防ぐために、左肩を沈み込むようにすれば、右肩も落ちなくなちます。
ボールが上がらないのでは、と考えるのはまさに余計な心配というものです。
この方がドライバーでも払うように打てるからティとロフトが生かされて、満足のいく高さの弾道を約束してくれるでしょう。
スポンサード リンク
それと腰を水平に回すことも必要です。わかりやすくいえばダウンスイングはベルトを水平に回して行なうようにチェックすることです。
意識としてベルトが地面と平行に回っているようであれば左肩があがることもありません。
ベルトを地面と水平に回す意識を持つと身体の回転も良くなります。
ちなみにベルトを水平に回すということは何もダウンスイングだけに限ったことではありません。
バックスイングでも同じことです。クラブがトップにいったとき左肩の回転につれて左腰も45度回っていますが、意識としてはベルトが水平に回っている感じがするでしょう。
 腰はスイングの間中、水平に回転させると考えていればゴルフスイングの基本そのものがずい分と楽に実現できるでしょう。
腰はスイングの間中、水平に回転させると考えていればゴルフスイングの基本そのものがずい分と楽に実現できるでしょう。
バックスイング、そしてダウンスイングの動きを後方から見るとわかりやすいものです。バックスイングでは左サイドを右へ回していく。
ダウンスイングはその逆です。左足が元に戻り右足のひざが左へ寄る動さをする前に手だけで打ちにいっては良くありません。
実はプロゴルファーのスイングは、割り合いとゆっくりですが、ここから先きの動きは早いものです。
この直後にはパッとクラブヘッドが前へ出ています。十分にタメているわけです。アマチュアでもいいリズムでクラブヘッドを振っている人は、これに近い動きになっています。
クォータースイング
クォータースイングではあごの軸を止めてまっすぐな軌道で振ることが大切です。スイングの軌道をもう一度チェックしてみましょう。
 ストレートな軌道で振れていればOKです。もし、そうでなければ、まずあご軸がぶれて動いていないかのチェックが必要です。
ストレートな軌道で振れていればOKです。もし、そうでなければ、まずあご軸がぶれて動いていないかのチェックが必要です。
クォータースイングで軸が動いてしまうミスショットのありがちな原因は、バックスイングを開始する同時に左ひざを内側(つまり右足側)に流してしまうことが挙げられます。
左ひざはスイングの間は動かないようにしっかりと我慢できていなくてはなりません。また、バックスイングの際にグリップの位置を上げてしまう例もあります。
これですと左肩が下がり、あごが傾きます。目線が地面との平行を失うとせっかくの振り子運動の軌道がゆがんでしまうわけです。
特にクォータースイングの場合、グリップの高さに注意を向けましょう。
アドレス、トップ、インパクト、フィニッシュ、どのポジションをとってもいつも同じ高さを維持するように意識しましょう。左ひざの我慢が、「あごで意識する軸」を不動に保っているのです。
スポンサード リンク
また、上半身が回転運動によって振り子運動の始点が移動することを防止するために、右肩をとめておく意識も高めておきましょう。
クォータースイングで7個のボールでスウェイをチェックしてみましょう。
5時-7時のクォータースイングで犯しやすいミスと原因についてもう一度考えて見ましょう。
バックスイングで身体が開いたり、フォロースルーで閉じてしまったりして、クラブフェースの向きも変わってしまうのは、ひじから先の部分、いわゆる手先でスイングするからです。
左腕とクラブは一本の振り子である意識がクォータースイングでは大切です。
振り子の支点が上下して起こるのがボールの手前の地面を叩くいわゆる「ダフリ」と「トップ」(ボールの頭を叩くこと)です。
ボールにクラブを当てようという意識があまりに強すぎて、右膝を動かしたり右肩が下がるとダフリが発生しやすいです。
また、左ひじを引き上げるように曲げてしまうとトップが発生しやすいです。
右わきを締めたり、右肩を後方に引くとインサイドにバックスイングしやすいでしょう。
インサイドにバックスイングした状態でクラブフェースの面を変えずにインパクトに移ると、左わきが開きフニッシュは外へとなります。
ボール投げで右手のフィーリングを高めるレッスンをもう一度練習しましょう。
右わきを開けすぎたり、ひじから先だけでバックスイングすると、結果的にクラブは外側に上がってしまいます。
アウトサイドにバックスイングしてクラブフェースの面を変えずにインパクトに移ると、左ひじが引けてフィニッシュは内へ向かいます。
左手一本でクォータースイングを試してみて振り子運動の感覚を思い出しましょう。